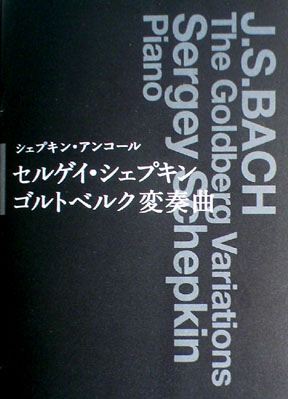この数年ポスト・グールドの呼び声高い、バッハのゴルトベルク変奏曲の新しい弾き手の登場がしばしば話題を呼んでいる。セルゲイ・シェプキンもその一人で、昨春の本邦デビュー・コンサートでゴルトベルク変奏曲を演って以来、日本でも急速に人気が高まっているようだ。1995年録音の同曲のCDも好調なセールスが推移しているらしい。そのピアニストが、一夜を限りにふたたび東京にもどってきた。6月24日、すみだトリフォニーホール。昨年と同じ会場で行われた「シェプキン・アンコール」にでかけてきた。
昨年のプログラムでは、バッハの「旅立つ最愛の兄に寄せるカプリッチョ」、グバイドゥリーナの現代曲との組合せだったのに対し、今回はオール・バッハ。イタリア協奏曲と2番のパルティータが前半で演奏された。
当夜のパフォーマンスで印象深かったのは、装飾音の多彩なこと。とくに前半二曲で強く感じたのだけれども、まるでチェンバロを聴いているかと思えるような、じつに軽やかな響きだった。グレン・グールドの演奏に慣れきった耳で受けてしまうと時に饒舌な感じがしなくもないが、スタインウェイがこのように鳴るなんて、ちょっと意表をつかれた快感でもあった。
後半のゴルトベルクは昨年もそうだったけれど、反復の省略はいっさいせずに長大なこの曲の魅力をよく引き出せていたのではないだろうか。たまにスピードが勢い余ったか、わずかに音の飛ぶところが聞こえたりしたがアクシデントというほどのことでもない。最後の変奏がはじまってようやく、固唾をのんで聞き入っていた聴衆の緊張がほぐれていくのを感じたような気がした。
 アリア・ダ・カーポが終わる。日本ではほとんど無名だった昨年のコンサートとは違って、評判を聞き付けてきた聴衆が多かったせいか、一部でスタンディング・オベーション、そして「ブラボー!」がわき起こった。演奏もさることながら、80分近くかかる大曲を表現しきったピアニストという存在に、誰もが敬服したのではないだろうか。
アリア・ダ・カーポが終わる。日本ではほとんど無名だった昨年のコンサートとは違って、評判を聞き付けてきた聴衆が多かったせいか、一部でスタンディング・オベーション、そして「ブラボー!」がわき起こった。演奏もさることながら、80分近くかかる大曲を表現しきったピアニストという存在に、誰もが敬服したのではないだろうか。
ターミネーターのように背筋をのばしてステージに現れた姿が印象的だった2006年のマルティン・シュタットフェルト以来、毎年ゴルトベルク変奏曲の演奏会を継続している、すみだトリフォニーホール。時として聴き手にもある種の忍耐を要求するような長大な曲だけれども、これをライブで聴くことができる喜びは何ものにも代え難い。(末ながく続けてください、U野さん!)